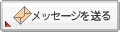2017年02月26日
87起:ナニやってんのエクアドルで(日々編)
2017年2月24日
今日でエクアドルに来てから232日、スペイン語の学習は322日、帰国まで497日となりました。今回は、実際にエクアドルのカニャル県トロンカル市でどんな生活をしているのか、青年海外協力隊としての私の日常を紹介したいと思います。任地であるカニャル県トロンカル市は標高も低く平地であるため、年間の気温が25度~30度という温暖な気候です。カニャル県の多くの市町村はシエラ地域(山間部)に属しているのに対して、トロンカル市はコスタ地域(海岸部)に分類されます。温暖な気候と雨を利用して、バナナ・キャッサバ・サトウキビの生産が盛んです。

山の上から市を眺める(撮影:todaken)

市のモニュメント(撮影:todaken)
今日でエクアドルに来てから232日、スペイン語の学習は322日、帰国まで497日となりました。今回は、実際にエクアドルのカニャル県トロンカル市でどんな生活をしているのか、青年海外協力隊としての私の日常を紹介したいと思います。任地であるカニャル県トロンカル市は標高も低く平地であるため、年間の気温が25度~30度という温暖な気候です。カニャル県の多くの市町村はシエラ地域(山間部)に属しているのに対して、トロンカル市はコスタ地域(海岸部)に分類されます。温暖な気候と雨を利用して、バナナ・キャッサバ・サトウキビの生産が盛んです。

山の上から市を眺める(撮影:todaken)

市のモニュメント(撮影:todaken)
朝くらいは胃袋を休めるの
深夜から朝にかけては、少し肌寒く感じ、朝は雨が降っている日も多いです。自宅は地元の一般家庭にホームステイさせてもらい、わたしは母屋から離れた小屋に住まわせてもらっています。最近の朝飯はコーヒーかマンサニージャコンミエル(カモミールティーの蜂蜜風味)とフルーツジュース。昨年の12月くらいまでは三食ガッツリ食べていたのですが、エクアドルの料理には油、塩、砂糖が多用されていることもあり、朝飯を抜いて昼食までは胃袋を休めるようにしています。身支度を整え、15分程度かけて徒歩で職場へ向い、8時には出勤します。出勤途中に曇り空の元にゴミが散乱している道を見るのは結構堪えますし、通り過がりの人から「チーノ!!(中国人・目が細い人・アジア人の意)」と呼ばれると、言い様のない憤り胸に溜まります。職場のオフィスには、カウンターパート(活動上の同僚)と事務担当と私の3名が常駐しています。赴任してからオフィスの場所が2回変わり、今の場所に落ち着きました。

部屋の中

出勤途中(撮影:todaken)
ぽっと出なオレの昼
ポっと出の日本人が、エクアドルの市役所で何をしているかというと、やっていることは大きく3つくらいあります。一つは、市内の学校で行う環境教育の出前授業と、それに使う資料や原稿を作る。2つ目に、コンポスト作成。コンポストとは生ごみを分解して堆肥化できる堆肥のことで、現在3種類のコンポスト(高倉式コンポスト・牛糞コンポスト・サトウキビ堆肥)を作成中です。高倉式コンポストはJICAも推奨している種類で、発酵液・腐葉土・米殻・木屑などを混ぜて作ります。利点としては匂いが少なく、分解が早いというところでしょうか。堆肥化できる容量は少ないので、堆肥の販路開拓や商品化は少し難しいです。
牛糞コンポストは牛糞・発酵した果物・腐葉土を混ぜたもので、こちらのサイトを参考に作りました。サイトでは腐った果物を用いてますが、私は代わりに果物、野菜、砂糖、塩をペットボトルに突っ込んだ簡単な発酵液を使い、屠殺場で作成しています。サトウキビ堆肥は不法投棄されているサトウキビの改善策として、これから最終処分場の近くで作る予定。作り方はこちらのサイトを参照しました。なぜコンポストを作っているかというと、任地のトロンカル市では将来的に生ゴミ処理施設(コンポストセンター)の建設を検討しているようで、その施設での処理方法の一つとしてノウハウを共有しています。その他、一般家庭での生ゴミ堆肥化、バナナ農園でも堆肥化を望む声もあるため、そういった方面でも技術移転できればいいなっと。
学校での出前授業(撮影:GAD LA TRONCAL)

同僚とコンポストを作ってみたり
そして、3つ目は同僚との意見交換。若者の力を活かした長期的な環境教育を考える私と、短期的でもやること自体が大切だと考える同僚の間で、意見が食い違うことも多く、ぶつかったことも多々ありました。ですが、最近は同僚がめちゃめちゃ忙しそうなので、大半のことは同僚の意見に同意しています。加えて、いくら長期的な計画や意見だとしても、2年後以降は自分が任地にいるわけではないので、同僚の意見を尊重したというのも昨今意見に同意している理由です。それに、意見のすれ違いなどから、同僚の仕事に支障がきたすことも避けたかったというのもあります。
協力隊の活動というと、協力隊員が主語になることが多いのですが、私は自分の活動よりも市役所が地域に貢献することを大切にしています。その貢献に対して、海外から来た日本人として何ができるのかを考えています。書き加えるならば、自分が楽しいと思えることには、活動の枠を超えて考えるのも好きです。世界的に見れば途上国と言われている国でも、地域で暮らす人達にとっては都ですし、人助けのために来ているというよりは、地域の人と一緒に考えることが大切なのかと。仕事ではない活動という広い意味合いだからできる身軽さを活かして、結果よりも過程を通じて、少しでも地域に貢献できれば嬉しいです。

ゴミ収集は日々問題だらけ

牛糞のコンポスは虫が多い
残りの午後から帰宅後
朝は冴えなかった曇り空も、昼間には打って変わって猛烈な太陽が差し込むこともあり、何やかんやと時間が過ぎて、12時~13時が昼休み(私は13時~14時)になります。同僚も私も昼食は食堂か自宅で楽しみます。エクアドルのアルムエルソと呼ばれる昼食は、スープ・メイン・ジュースの3点セットがもっぱら一般的です。しかし、料理にはジャガイモやトウモロコシや豆などの炭水化物が多いので、私は昼食の際には白米を抜いています。17時になると自宅へ帰宅して、夕食までの間は衣類の洗濯やスカイプを用いたスペイン語のクラスを受けたり。19時には夕食を取り、その後の余暇はスペイン語の勉強、日本で使っていたパソコンのハードディスクのデータの整理、YOUTUBE鑑賞、三線の練習などをしています。夜が更けるとシャワーを浴びて、ベットで小説を読んで24時には就寝。何と規則正しい生活なんでしょうね。

ホストファミリーの作ってくれる昼食

市民の足になっているモトタクシー
カンキョウキョウイクで派遣中
市内の学校を巡回しては「ゴミを道端に捨てるなー」「ゴミ捨てるとこうなるぜー」「日本ではゴミをこんな風にしてるぜー」みたいなことを言ってます。同僚の都合で、最近は学校巡回はしていませんが。ゴミが捨てられることで生まれる雇用もあるので、その点も含めて考えていかないといけのかもしれません。市内では80~90名のゴミ収集員(関連する人も合わせると100名近く)が働いており、収集車と3輪車で家庭ゴミや道端のゴミを収集しています。道端のゴミが先に出たのか、収集員が先に雇用されたのか知りませんが、彼らの雇用にもなっているというのも事実です。加えて、任地のトロンカル市のみならず、他市町村というか南米の多くの地域ではゴミのポイ捨てが日常茶飯事に行われています。そして、彼らの多くは「ゴミのポイ捨てが何となく悪いこと」というのは分かっているんです。忘れてならないことは、石油由来の製品やプラスチックなどは先進国から持ち込まれたものだということ。しかし、外部から持ち込まれた製品の扱い方や活用方法は国によって異なるわけで、エクアドルとして環境や教育に力を入れるかが試されてところでもあり、去る2月19日に行われた大統領選挙(4月に上位2名により決戦投票予定)によって、今後の動向が気になります。

中心街(撮影:Misa Kawamura)
メインの通り
そんなこと知ってるわ
「ゴミを捨てると衛生的に…」
「環境にも悪いし…」
「下水が詰まるし…」
地域に住む人にとっては「環境に良い・悪い」より「お金欲しいなぁ」「今は何がしたいのかなぁ」「もっと稼げる仕事はないのかぁ」の方が実感のある問題で、凄く大切なことなのです。ゴミを捨て続けても、「誰かが」「私の見えないところで」「何かをしてる」「だから大丈夫」というのが正直なところでしょう。でも、これは日本も似ている気がします。日本でも多くのゴミが焼却後に最終処分場に積まれ、リサイクルされてはいるものの石油由来の商品や食品の消費は促される、ゴミは排出され続けています。経済基盤の上で庶民の消費は大切な原動力とも言えるため、消費を一概に害とは言えませんが。幸いなことに日本では、学校・社会・家庭という三大教育の中で環境に対する意識付けがされています。学校教育では給食当番や掃除の時間を通じて、社会教育では区内清掃や近所の目などの効果があって、家庭教育では家の中で躾を受けて、義務教育を終える頃には「激しいポイ捨て」や「モラルのないゴミ捨て」をしない程度の人間になります。
しかし、日々の生活の中では何も考えずにゴミは出され続けていますし、一方で毎日毎日隙なくゴミのことを考えている人は少ないでしょう。日本では戦後の公害問題と高度経済成長を通じて、先人方がゴミの処理工程を確立してくれました。教育と教訓から結果的に、他国に比べると日本の道端にはゴミを見かけることは少ないですが、最終処分場にゴミが山積みになっているという事実には変わりありません。日本もエクアドルも、日々のゴミより、日々の生活が大切な人が大半で、大きな違いといえば環境に関する教育を受けているか受けていないか、という点ではないでしょうか。ただ、一概には言えませんが、私の周りにいるエクアドル人の中には、短中長期なんて言葉を飛び越して瞬間的な欲求に従いやすい人が多く、周りのことよりは自分のことが優先という印象を受けます。若干高い教育を受けている人は、長期的に物事を考えようと励んでいる人がいることも事実です。また、人生として何が幸せなのかということと、上記のことは比例しないでしょうから、エクアドルと日本のいずれが幸せかなんて比較するのは難しいですし、比べることでもないかと。

収容量を越えかけている最終処分場で金目の物を探して生計を立てるオジサン
つらつらと綴ったわけですが、お陰様で元気にやってます。今度は任地の紹介をしたいと思います。
OLEDICKFOGGY /シラフのうちに