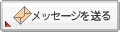2018年02月21日
91起:ふとした衝動から、南米にある「オキナワ」を探しに出かけた
”南米だからこそ”の、沖縄に触れたい
雨季のため冴えない空模様が続きますが、私は元気です。
雨季のため冴えない空模様が続きますが、私は元気です。
指折り数えていた730日間という南米エクアドルでの生活も、593日目。
毎朝目覚める度にベッドに掛かる蚊帳を眺めてエクアドルにいることを確認していた赴任当初の新鮮な気持ちも薄れ、充実とも過失とも言えない、ただ連続したときを南米で暮らしながら、密かに計画していた旅行がありました。
それが“ボリビアのオキナワ訪問”です。また、オキナワで奮闘している同期の協力隊員が滞在しているうちに行ってみたいと思い、3泊5日で2カ国訪問という弾丸旅行を決行。その時の様子を紹介したいと思います。
決行初日、グアヤキル(エクアドル)‐リマ(ペルー)‐サンタ・クルス(ボリビア)‐オキナワという経路でオキナワ入り。

それが“ボリビアのオキナワ訪問”です。また、オキナワで奮闘している同期の協力隊員が滞在しているうちに行ってみたいと思い、3泊5日で2カ国訪問という弾丸旅行を決行。その時の様子を紹介したいと思います。
決行初日、グアヤキル(エクアドル)‐リマ(ペルー)‐サンタ・クルス(ボリビア)‐オキナワという経路でオキナワ入り。

オキナワの陸路は自家用車で制す
早朝にも関わらず同期のSさんとオキナワ住民の真栄城さんがサンタ・クルス空港まで送迎に来てくれました。
地元の方が自家用車と凸凹の近道を駆使するとサンタ・クルス市‐オキナワは1時間強の道のりですが、乗り合いタクシーで乗り継ぎをして4時間、個人タクシーで直行しても2時間程度かかります。
見渡す限り畑の風景を越えると、数件の家と舗装された道が。「もしかて、これがオキナワなのか!?ただの南米の田舎町じゃないか」というのがオキナワの第一印象でした。
サンタ・クルス県オキナワⅠ市内には第1から第3までのコロニア(区域)があり、第1が100世帯、第2は40世帯、第3は30世帯ほどの沖縄系移民の方が暮らしているそうで、最初に私が到着したのは第2コロニアでした。
コロニアの移動は基本的に自家用車のため、コロニアの方にお世話になりっぱなしでした。
第2コロニア青年会館

オキナワでの初めの食べ物は、紅白餅と白饅頭

日用雑貨や食品、豆腐まで取り扱っている第2コロニアの商店
オキナワの希望、学校訪問
長旅の上に睡眠不足だったこともあり、ボケッとした頭の中でオキナワの実態が掴めないうちに、同期のSさんが活動をしている学校へ。
真夏の沖縄を思い出す程の強い日差しの中、子ども達と若い青年が野球をしているではありませんか。沖縄県の甲子園に対する情熱はズバ抜けていると有名ですが、南米のオキナワも・・・、血は争えないということか!?っと思っていたのですが、実は福岡大学とJICAボリビアが連携している事業の一環らしく、青年の方々は青年海外協力隊の野球隊員(短期)の皆さんでした。
スーパー爽やか超好青年の彼らと、すこぶる純粋な子ども達の交流にホッコリしながら、強烈な太陽の暑さにもホッコリやられかけました。
野球部の皆さんは約1ヶ月かけてボリビア国内を回りながら、指導をするそうです。野球だけではなく昼食・授業・アクティビティを通じて先生や子ども達との交流も行われていたので、お互いにとって忘れられない思い出になったことでしょう。
昼食には先生手作りのウドンチャンプルー、空揚げ、漬物、味噌汁、コロニアオキナワ特製の牛串てんぷら、油味噌、サーターアンダギーなどが振舞われ、沖縄の味を堪能することができました。

学校の校舎

野球を指導しているスーパー爽やか大学生

先生たちが丹精込めて作ってくれた日本・オキナワ料理
オキナワの都会は第1コロニア
学校を後にすると、車で30分ほどの場所にある第1コロニアへ移動。
第2に比べて道路も舗装され、沖縄の方が関係している商店・病院・記念館・建物も多く見受けられ、同時に中南米で多くの割合を占めるメスティーソと呼ばれる褐色系の人も多く住んでおり、沖縄とボリビアが混ざっている空間が特徴的でした。
夕食は同期のSさんの他に、同市の学校で活動する協力隊員の方、奨学金で沖国大へ1年間通っていた青年の計4名で、沖縄の方が経営する焼鳥屋さんへ。
沖国大に通っていたという青年は、実は私が沖縄にいた頃に住んでいた頃に活動していた長田区青年会のエイサーを見たことがあるそうで、元御近所さんだということが判明。さすが沖縄。
肝心の焼鳥は肉汁溢れる大きなムネ肉に特製の醤油ダレが絶妙な合わせ業、焼鳥1本につきジャガイモが一切れ付いてくるのがボリビア流。更に肉と野菜の盛り合わせも一緒に、もうビールが止まりません。ただし、食べている間だけで蚊に20箇所くらい刺されました。
その後、沖縄の方が経営しているカラオケに行くと、福岡大の学生と現地の青年達が熱唱中。あっというまに、夜は更けました。
舗装されている道の脇から砂埃が舞い上がる第1コロニアのメイン通り

レストラン比嘉EL TIO(孫の意)と奥はウチナーという商店

焼鳥とジャガイモ
さよならオキナワ、どうもサンタ・クルス
オキナワ滞在最終日。
前日の疲れからか、ほど良い堅さのベッドとお邪魔した家の雰囲気があまりにフィットしすぎたせいか10時間も寝てしまいましたが、友人に起こしてもらい朝から移民博物館の見学に行ってきました。
移民の歴史が当時の農具や生活用品と共に紹介されており、コロニア内での行事や地域活動なども写真と説明文で解説されていました。
土と森以外は何も無かった時代、開拓時には流行病により亡くなった人もいたようで、泥水が真水のように澄み切るまで時間がかかるように、生活が安定するまで先人達の並々ならぬ苦労が展示の説明文から読み取れます。
移民の歴史についてはコチラを参照。
その後、青年会と福岡大学が野球の交流戦を行うこと言うことで、試合の見学をしながらロクロという米とスパイスと肉を煮込んだ料理(中にはボロボロジューシーと呼ぶ人も)を頂き、後ろ髪を引かれながらオキナワからサンタ・クルスへ出発しました。
いま思い返しても、最初から最後まで世話になりっぱなし、楽しませてもらいっぱなしのオキナワ滞在でした。
しかし、眩いながらの笑顔の影には、物語れないような移民の苦労、現地での差別、自然災害、色んな偏見に晒されてきた過去があったことを心の隅に置いていないといけないとも感じました。

移住博物館内の展示物

鍋イッパイに作られた美味美味なロクロ、お祝いの時にはヤギを潰すこともあるそう

中心街の公園にある鳥居のモニュメント
ボリビアの誇りと故郷
オキナワで話されている言葉ですが、日系の方は日本語・スペイン語です。一世・二世のような中年・年配の方が話すのは沖縄で聞かれるようなウチナー訛りの日本語又はウチナーグチ、青年は人によって若干の差があるものの若者の言葉の日本語を話しますが、子どもは日本語での会話が難しい子もいるようで、それは家庭環境や本人の意欲により異なるとのことでした。
また、ひと昔前に比べると沖縄系移民同士での結婚だけではなく、ボリビア人と家庭を持つ人も増え、家族の在り方が多様的になっており、日本語習得は地域内の課題になっているようです。
使用言語が家族・学校の会話はスペイン語、日系の友達とは日本語、放課後の日本語の補習授業で自発的に学ぶ、という一見すると家庭・社会・学校教育によって学習気概が均等にあるように見えますが、家庭・学校教育での語学習得の時間と、ボリビアの国語はスペイン語であることを考えると、日本語の習得が遅くなるのは頷けます。
ボリビアで生まれ育った日系の人にとって、アイデンティティはボリビア人として祖国のボリビアを想うのが自然であり、沖縄・日本はルーツでありながらも海外なのかもしれません。
そんなボリビアの片田舎で、ここまで沖縄のコミュニティーが色濃く残っている地域は貴重なのかもしれません。
いつまでこのような姿を見られるかは分かりませんが、ボリビアの発展を担っていくオキナワの人達の強かな優しさに感銘を受けたことは紛れもありません。
また、各コロニアには青年会があり、15歳から30歳までの地域の青年で構成されており、地域活動や琉球国祭り太鼓の演舞などを行っているそうです。宜野湾市で青年会活動に熱中していた自分としては、この事実に一番感動しました。

第1青年会のティーシャツの胸にはサッカーとビールのエンブレム

毎年カルナバルの時期に作っているというオキナワティーシャツの胸には干支

歴史を感じる第1青年会のクーラーボックス
ペルーで見た華やかな沖縄祭り
ボリビア・オキナワを去った翌日、同時期に隣国のペルー・リマ市で開催されていた沖縄祭りへ遊びに行ってみました。
ペルー中心街からバスで1時間ほどの場所にある沖縄県人会館、こちらで沖縄祭りが開催されていました。この祭りの1週間ほど前から世界の若者ウチナーンチュ大会も開催されており、沖縄をはじめアメリカ大陸を中心に各国から沖縄に縁を持つ青年や関係者が来場していました。
舞台ではかぎやで風、民謡、ポップス、琉球国祭り太鼓まで、沖縄一色のプログラムが観客を魅了していました。
前日には沖縄からスペシャルゲストとしてHYも出演してたため、この日の祭り会場にも遊びに来ていたそうです。
観客席を囲むように出店が立ち並び、ちょうど中南米のカルナバル(謝肉祭)の時期にあたっていたためプールも人が沢山、グラウンドでは空気の入った大きな遊具に興じる子ども達も見受けられました。
それらの建物が全てペルー沖縄県人会の所有というから驚きですが、県や国の政策として移民を推奨していた過去を考えると、それなりの恩赦を受け取る権利があるのも頷けます。
会場では嘉手納町の青年会メンバーとも落ち合えたため、彼が参加していた若者ウチナーンチュ大会の青年達とも話す機会に恵まれました。
アルゼンチン・アメリカ・ペルー・ブラジルなど、世界各国から集まった沖縄に血縁のある青年達、英語・日本語・スペイン語の交じり合い生まれる眩しいほどの笑顔には国境を越えた一繋ぎの友情を見た気がしました。
繋がった縁が交流を超え、新たに何かを生み出す原動力になることを願っています。

駐車場には沖縄県の各市町村のプレート

幕開けのかぎやで風

沖縄そばも沖縄と変わらない優しい味
なぜに沖縄を探したのか
普天間飛行場のヘリコプターが沖縄国際大学に墜落した翌年、当時18歳だった私は同大学へ通い、卒業後も仕事や青年会活動に興じるために約10年の間宜野湾市で生活をしました。
私はウチナーンチュではありませんし、愛媛生まれの親父と東京生まれの母の間に生れ落ち、東京で生まれ育ったという強い自覚もあれば、一方で沖縄の地域や青年会から沢山のことを教えてもらったとも感じており、しかし特段ウチナーンチュに生まれ変わりたいとも思っていません。
ただ、沖縄を想い、沖縄に暮らす人や息づく文化に淡く恋焦がれる気持ちを胸に、永住したい場所の一つとしても考えています。
そんな想いと海外に息づく沖縄を知りたいという気持ちから、今回の旅を計画しました。
当初はどこかで南洋小唄・移民小唄などの曲を披露しようとエクアドルの自宅で黙々と練習をしていましたが、実際に移民を経験した方々の歴史や現地での声を聞いて見ると、何とも唄えるような立場でないと思いました。
それは、歌詞に思いを込めるには見てきた物や経験が足りず、仮に人前で披露するにも旅の最中謎の喉カスカス病になってしまい歌える状態でなかったからです。結果として「お前が歌える時じゃない」と言われているようで、今回は知って、繋がって、楽しむことに集中できました。
海外移民の歴史は沖縄県だけではなく日本各地にもありますが、今日までの移住先での活発な活動や県内での留学生受け入れ等の沖縄県との関係性などは独自性に富んだものだと感じています。
オキナワから3時間程度の場所にあるサン・フアン地区にも、九州からの移民の方が多く住んでいるそうです。
最後に、日本のみならず、世界各地には生まれ育ったの土地から離れて生活をしている、異国で生活せざる終えない人達が沢山いることも忘れてはいけません。
今回の旅でお世話になった皆さん、ありがとうございました。

学校の日本語教室で指導する同期
コロニアの小学校には数十丁の三線
ペルー沖縄祭りの全景